JTB総合研究所 主席研究員 吉口克利氏
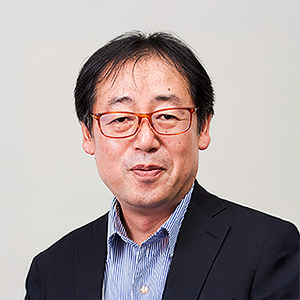
吉口 克利(JTB総合研究所 主席研究員)
研究・専門分野
インバウンド・観光マーケティング(調査・分析)・観光地域づくり等
JTB総合研究所主席研究員、吉口克利さんには、千葉大学とのクロスアポイントメント教員として、本卓越大学院プログラムを担っていただいており、企業メンターのほか、インターンシップの担当をお願いしています。また、JTB総合研究所のお仕事で、日本全国を飛び回りながら、同時に2024年度まで大学院博士後期課程に在籍、「観光まちづくり」をテーマに論文を執筆して学位を取得されています。
JTB総合研究所主席研究員としてのお仕事を教えてください。
吉口:JTB総合研究所は、観光関連全般のコンサルティングを行っている、JTBグループの会社です。私はそこで、国や自治体の観光振興事業、例えば、地域での観光振興計画の策定や、DMOといわれている観光推進団体の立ち上げ、コンテンツの造成、プレイス・ブランディングなど、様々な取り組みのお手伝いをしています。そして、それらのプロジェクトを検討する上でまず必要となるのが各種調査や様々なリソースから収集したデータの分析です。もともと私はマーケティング・リサーチの業界で多くの企業のリサーチに携わってきましたので、マーケティング視点でプロジェクトを企画できることが強みと考えています。
現在の観光は非常に多様化しており、訪れた地域の生活や文化を体験してみたい、暮らすように滞在してみたい、地域の取り組みに参加してみたいなど、様々なスタイルの旅行が行われています。このような観光や交流のトレンドを把握して、有効な観光振興策を提言する一方で、地域におけるサスティナブルな観光の在り方などについても考えるといった、観光や交流を通した地域づくりのプロジェクトを、常に5本から10本ほど抱えて、各地を飛び回っています。
ありがとうございます。ところで吉口さんは先ごろ学位請求論文を執筆されて、博士の学位を取得されていますね。学位請求論文はどのようなテーマで執筆されたものですか。概要を教えてください。
吉口:論文のタイトルは『クリエイティブなアクターが生まれ、活かされ、集まる「まち」の要件』という、博士論文らしからぬタイトルをつけてしまったのですが、いかがでしょう。
「まちづくり」、「観光まちづくり」といった言葉は皆さんもよく耳にしていると思いますが、それらは、行政で企画された地域ぐるみの取り組みとして、自治体が行っているものと大半の方が思っているのではないでしょうか。しかし、仕事で様々な地域を見てきましたが、地域を活気づけている取り組みの多くは、純粋に個人の趣味や関心などから周囲を巻き込んで始められた小さな活動がスケールを増して、地域としての取り組みに見えているケースが多いのです。一方で、地域の人口減少や経済の衰退などを課題に掲げた行政などによる地域振興策は、なかなか地域での継続的な取り組みにつながりません。
私は社会学の視点から、地域を更新している個々のアクターたちに焦点を絞り、彼らや、彼らの実践がどのような環境の中で生まれ、活かされているのか、それによって地域に何がもたらされているのか、彼らの実践の意味を捉えるにはどのような理論フィルターが必要かといったことを、長野県の上田市という地方都市でフィールドワークを続け、論文にまとめました。
お仕事の内容と学位請求論文における研究テーマには通じるところがありますね。お仕事に従事しながら研究論文をまとめるのは大変だったと思いますが、研究に打ち込むことでそれがお仕事に裨益した部分はありますか。
吉口:学部時代に社会学を専攻していたこともあり、社会人になっても、自分が携わった仕事や、それを取り巻く環境に対して、違和感を持つことが度々ありました。学位論文も地域の皆さんと様々な事業を行う中で常に感じていた違和感=「問い」を客観的に整理して、行政や地域の方たちにも同じように違和感を持ってほしい、考えてほしいという思いでまとめたものです。現場で様々な調整をしながらどうにかプロジェクトを行うことができても、それが地域としてほんとうにプラスになっているのかを、様々な議論を参照しながら反省的に捉えるプロセスは重要です。という意味では、私の中で“仕事と研究”、“産・学”という区別はあまりなく、どちらもライフワークという感覚です。

これからは大学院人材、とりわけ博士人材がアカデミア以外の場所で活躍することが期待されています。企業研究所の業務と大学院における研究の両者を経験された立場から、大学院生の学びやキャリアについての助言があればお願いします。
吉口:私が関わっている、観光や地域振興などの領域は横断的な思考が必要であり、観光学だけではなく、アカデミックな領域では、社会学、人文地理学、文化人類学などから、観光産業という面では経営学など、多くの領域から考察されています。大きな社会の変化の中で、横断的な思考のニーズは観光だけでなく多くの領域で求められるようになり、大学院生、特に博士課程の皆さんの研究領域を活かせる場は増えているように思います。また、リサーチ・クエスチョン=「問い」をいかに立てるか、研究の軸をどこに置くかといったことを考え、研究を深めていく訓練ができている院生の皆さんのスキルは、アカデミア以外の場でも非常に重要なスキルだと思います。ですので、皆さんの研究とアカデミアの外側とのつながりについて意識的に考えてほしいですし、課程修了後のキャリア形成の場としても、皆さんの知見を活かせそうな取り組みに目を向けていただければと思います。
最後に人文社会科学系大学院の教育について、企業人としての観点から要望があればお教えください。
吉口:周囲を見ても私のように働きながら、学びたい、研究をしたいという人は確実に増えています。逆に、修士課程、博士課程を修了してから、企業や行政などに就職し、そこでの経験を経て、改めて研究すべき「問い」を発見する人もいると思います。人文社会科学系大学院の一部にこのような思いを持った人たちが交流し、活発に議論しあえる「つながりの場」というか、新たな創発が次々に生まれるような「場」ができるといいですね。
微力ながら私もそのような場づくりのお手伝いができればと考えています。




